
一級建築士の構造文章題解説。鋼材・金属について解説しています。
※本動画はR7年度改正前に作成した動画です。
動画内で解説した問題
※動画を見るだけではなく、見たら必ず自力で解けるかどうか確認してください。
問題をクリックすると回答が表示されます。
問題1:ステンレス鋼は,約11%以上のクロムを含む合金鋼であり,炭素鋼に比べて,耐食性,耐火性等に優れている
回答:◯
問題2:鋳鉄は,延性が劣り,曲げモーメントや引張力に対して脆い性質があるので,鉄骨構造の構造耐力上主要な部分に使用する場合,使用部位が限定されている
回答:◯
問題3:鋼材の引張強さは,常温から600℃までの範囲において,温度の上昇に比例して低下する
回答:✕
解説:鋼材の引張強さは,一般に100℃付近で一度常温の値より低下し,250~300℃付近で上昇し最大となる。更に高温になると, 急激に低下し500℃では約1/2になる。
問題4:一般構造用圧延鋼材(SS材)は,鋼材温度が約350℃になると,降伏点が常温時の約2/3に低下する
回答:◯
問題5:焼入れされた鋼材の強度・硬度は低下するが,靭性は向上する
回答:✕
解説:焼入れは鋼材の硬さを増大させる目的で行われるが,靭性は低下する。そのため,焼入れ後には焼き戻しを行うのが一般的である。
問題6:シャルピー衝撃試験の吸収エネルギーが小さい鋼材を使用することは,溶接部の脆性的破壊の防止に有効である
回答:✕
解説:シャルピー衝撃試験は切欠き試験片に衝撃力をかけて,破壊に要したエネルギーの大小によって衝撃破壊に対する抵抗力を評価するものである。
シャルピー衝撃値が小さい(吸収エネルギーが小さい)ほど,小さいエネルギーで破断する脆い材料である。一方,シャルピー衝撃値が大きい。
(吸収エネルギーが大きい)ほど,破壊に要するエネルギーが大きくなり,強く粘り強い材料である。
問題7:建築構造用ステンレス鋼材SUS304Aについては,ヤング係数はSN400Bより小さいが,基準強度は板厚が40mm以下のSN400Bと同じである
回答:◯
問題8:炭素鋼,ステンレス鋼(SUS304A材),アルミニウム合金の線膨張係数の大小関係は,炭素鋼>ステンレス鋼>アルミニウム合金である
回答:✕
解説:普通鋼材のSS400材の線膨張係数は,1.12×10-5/℃程度であり,ステンレス鋼(SUS304A材)は1.73×10-5/℃程度であり, アルミニウム合金は2.35×10-5/℃程度であるので,設問の符号の向きが逆である。
問題9:アルミニウム合金の線膨張係数は,炭素鋼の約1/2倍である
回答:✕
解説:普通鋼材のSS400材の線膨張係数は,1.12×10-5/℃程度であり,アルムニウム合金は2.35×10-5/℃程度であるから, アルミニウム合金の線膨張係数は鋼材の約2倍である。
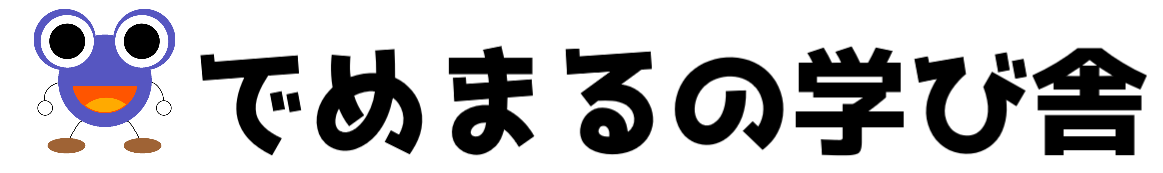

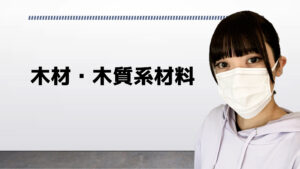
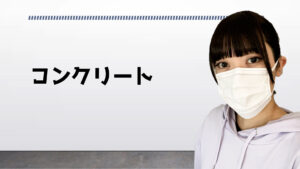
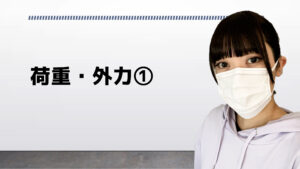
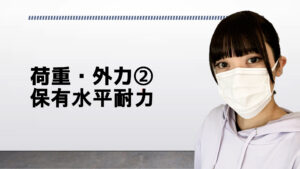
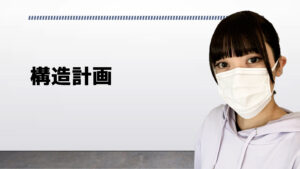
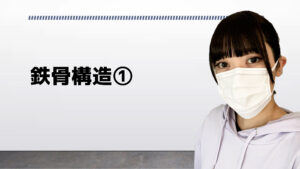
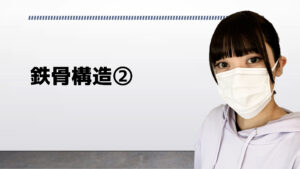
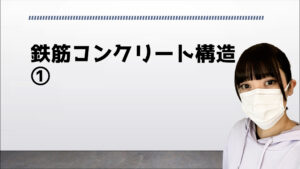
コメント