
一級建築士の構造文章題解説。保有水平耐力について解説しています。
※本動画はR7年度改正前に作成した動画です。
動画内で解説した問題
※動画を見るだけではなく、見たら必ず自力で解けるかどうか確認してください。
問題をクリックすると回答が表示されます。
問題1:Qunは,各階の変形能力を大きくし,建築物の一次固有周期を長くすると大きくなる
回答:✕
解説:必要保有水平耐力Qunは以下の式で表される.
Qun=Ds・Fes・Qud
ここで,Ds:構造特性係数,Fes:形状係数,Qud:大地震を想定し,Co≧1.0として計算した地震層せん断力
構造特性係数Dsは,地震エネルギーの吸収能力による地震力の低減を表す.架構が靱性に富む(塑性変形能力が大きい)ほど,減衰が大きいほど,地震エネルギーの吸収は大きくなるので,Dsは小さくなり,Qunは小さくなる.
また,建築物の設計用一次固有周期Tは,Qud(=Wi×Z×Rt×Ai×Co)に影響するが,Tが大きくなると,Rtは小さくなるがAiは大きくなるため,TとQunとの相関を明言することは難しい
問題2:地震時の変形に伴う建築物の損傷を軽減するために,靱性のみに期待せず強度を大きくした
回答:◯
問題3:建築物の耐震性は,一般に,強度と靭性によって評価され,靭性が低い場合には,強度を十分に大きくする必要がある
回答:◯
問題4:鉄筋コンクリート構造の保有水平耐力計算において,全体崩壊形を形成する架構では,構造特性係数Dsは崩壊形を形成した時点の応力等に基づいて算定した
回答:◯
問題5:鉄筋コンクリート構造の耐震計算ルート3において,脆性破壊する柱部材を有する建築物を対象として,当該柱部材の破壊が生じた時点において,当該階の構造特性係数Ds並びに保有水平耐力を算定した
回答:◯
問題6:鉄筋コンクリート構造の保有水平耐力計算において,柱の塑性変形能力を確保するため,引張鉄筋比ptを大きくした
回答:✕
解説:断面の一辺に多数の鉄筋を配置したり,隅角部に太い鉄筋を配置した場合などのように引張鉄筋比が大きくなると,脆性的な破壊形式である付着割裂破壊が生じやすくなる.よって,塑性変形能力は低下する
問題7:梁部材の種別をFAとするために,コンクリート設計基準強度Fcに対するメカニズム時の平均せん断応力度τuの割合が,0.2以上となるように設計した
回答:✕
解説:構造特性係数Dsを算定する際に定める部材種別は,部材の靭性能に関する指標により,柱及び梁はFA~FDに,耐力壁はWA~WDに分類される.梁部材の靭性能は,FAが最も高く,コンクリート設計基準強度Fcに対するメカニズム時の平均せん断応力度τuの割合(τu/Fc)及び部材の破壊形式により定める.
τu/Fcにおいて,Fcが同じ場合,τuが小さくなるほど,一般に,せん断破壊が生じる可能性が減り,靭性能が高くなる.従って,τu/Fcが0.2以上となる場合は,せん断破壊の可能性が高まり,靭性能は低下する.
問題8:鉄筋コンクリート構造の保有水平耐力計算において,梁の塑性変形能力を確保するため,崩壊形に達したときの梁の断面に生じる平均せん断応力度を小さくした
回答:◯
問題9:保有水平耐力は,建築物の一部又は全体が地震力の作用によって崩壊形を形成するときの,各階の柱,耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和としてもよい
回答:◯
問題10:「曲げ降伏型の柱・梁部材」と「せん断破壊型の耐力壁」により構成される鉄筋コンクリート構造の保有水平耐力は,一般に,それぞれの終局強度から求められる水平せん断力の和とすることができる
回答:✕
解説:保有水平耐力は,建築物の一部又は全体が地震力の作用によって崩壊メカニズムを形成する場合において,各階の柱,耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和として求められる値であり,材料の種類及び品質に応じて定められた材料強度によって計算する.
曲げ降伏型の柱,はり部材(靭性部材)とせん断破壊型の耐震壁(脆性部材)との混在により構成される架構の保有水平耐力は,通常,耐力壁が先に終局に達し耐力が低下するので,靭性部材(ラーメン)と脆性部材(耐震壁)の終局時せん断力の和を保有水平耐力とすることができない.
それぞれの部材が破壊するときの変形状態において各部材が負担する水平せん断力の和として求める
問題11:「限界耐力計算」において,積雪,暴風及び地震のすべてに対して,極めて稀に発生する荷重・外力について建築物が倒壊・崩壊しないことをそれぞれ検証することが求められている
回答:◯
問題12:損傷限界は,建築物の耐用年限中に少なくとも一度は発生する程度(中程度)の地震力の作用後において,建築物の安全性,使用性及び耐久性が低下せず,そのための補修を必要としない限界である
回答:◯
問題13:保有水平耐力から安全限界耐力を算定する場合,建築物のいずれかの階が最初に保有水平耐力に達するときの建築物の耐力を安全限界耐力とする
回答:◯
問題14:限界耐力計算において,建築物の安全限界固有周期が同じ場合,建築物の減衰が大きいほど地震力は小さくなる
回答:◯
問題15:限界耐力計算において,塑性化の程度が大きいほど,一般に,安全限界時の各部材の減衰特性を表す係数を大きくすることができる
回答:◯
問題16:限界耐力計算における安全限界固有周期は,建築物の地上部分の保有水平耐力時の各階の変形により計算する
回答:◯
問題17:安全限界の検証に用いる標準加速度応答スペクトルの大きさは,損傷限界の検証に用いる大きさの5倍である
回答:◯
問題18:振動の固有モードの節(不動点)は,1次の固有モードの場合には,固定端のみの1個であり,2次,3次と次数が増すごとに,1個ずつ増える
回答:◯
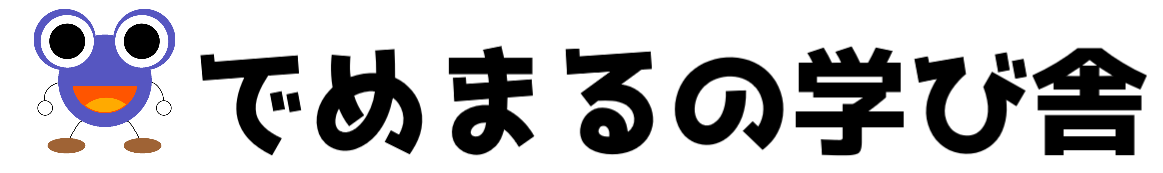

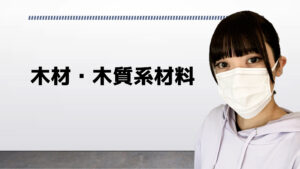
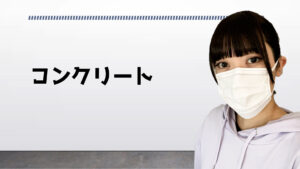
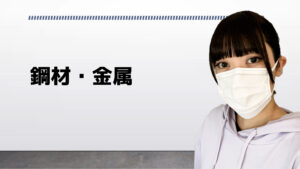
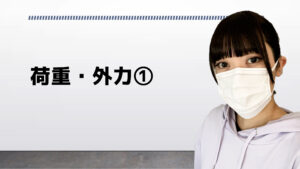
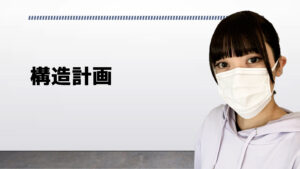
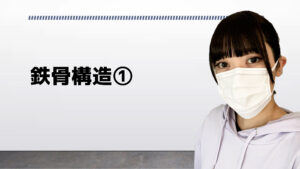
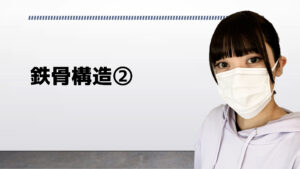
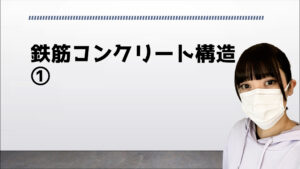
コメント