
一級建築士の構造文章題解説。前回に引き続き鉄骨構造について解説しています。
※本動画はR7年度改正前に作成した動画です。
目次
動画内で解説した問題
※動画を見るだけではなく、見たら必ず自力で解けるかどうか確認してください。
問題をクリックすると回答が表示されます。
問題1:応力が許容応力度以下となった梁のたわみを小さくするために,SN400Bから同じ断面寸法のSN490Bに変更した
回答:✕
解説:弾性変形はヤング係数と部材断面から定まる断面2次モーメントに反比例する.鋼構造の場合,鋼材のヤング係数は一定であるので,SN400B材の代わりに同断面のSN490B材を用いても変形を小さくすることはできない.変形を小さくするためには断面を大きくするか,材長を短くするのが有効である
問題2:引張力を負担する筋かいの設計において,筋かいの靭性を確保するため,その降伏耐力は,接合部の破断耐力に比べて大きくする必要がある
回答:✕
解説:鉄骨構造の筋かい材にある程度の塑性変形を期待し,現実的な設計を行うため,端部および接合部の破断耐力は筋かい材の降伏耐力より十分大きくしなければならない.
問題3:鉄骨構造のトラスの弦材(げんざい)の座屈長さは,精算によらない場合,構面内座屈に対しては節点間距離とし,構面外座屈に対しては横方向に補剛された支点間距離とする
回答:◯
問題4:鉄骨構造,地上3階建の構造設計に関して,柱とはりにH形鋼,筋かいに山形鋼を用い,はり間方向をラーメン構造,けた行方向を筋かい構造によるものとする場合,ベースプレート及びアンカーボルトからなる露出柱脚は,軸方向力及びせん断力とともに,回転量の拘束に伴う曲げモーメントに対しても設計した
回答:◯
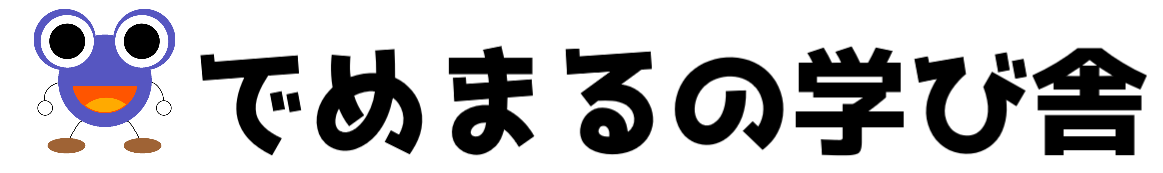

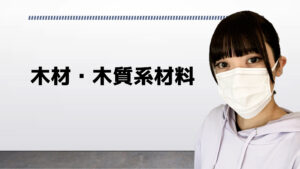
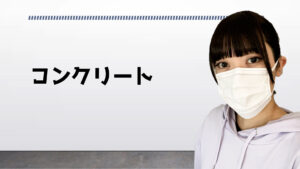
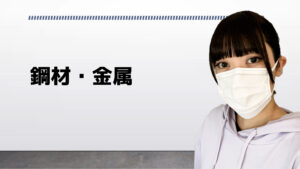
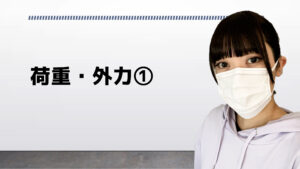
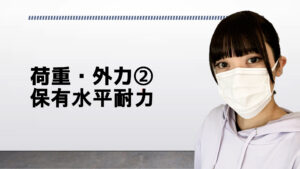
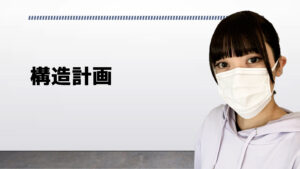
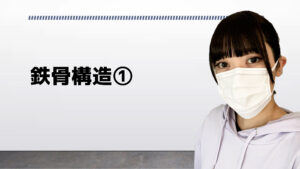
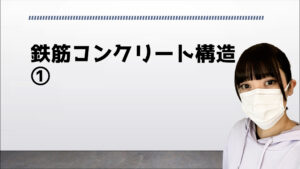
コメント