
一級建築士の構造文章題解説。鉄筋コンクリート構造について解説しています。
※本動画はR7年度改正前に作成した動画です。
動画内で解説した問題
※動画を見るだけではなく、見たら必ず自力で解けるかどうか確認してください。
問題をクリックすると回答が表示されます。
問題1:鉄筋コンクリート構造計算規準によると,コンクリートの気乾単位体積重量が同じで設計基準強度が2倍になると,コンクリートのヤング係数もほぼ2倍となる
回答:✕
解説:Ec=3.35×104×(γ/24)2×(Fc/60)1/3 (N/mm2).コンクリートのヤング係数はコンクリート設計基準強度Fcと単位容積重量γから定まる.設計基準強度が2倍になると,コンクリートのヤング係数は,21/3倍となり,2倍とはならない
問題2:コンクリートのヤング係数は,圧縮強度が同じ場合,一般に,使用する骨材により異なる
回答:◯
問題3:鉄筋コンクリート構造の超高層建築物に異なる強度のコンクリートを使用するので,コンクリートの設計基準強度ごとに,異なる単位体積重量を用いて,建築物重量を計算した
回答:◯
問題4:鉄筋コンクリート構造の梁の長期許容曲げモーメントを大きくするために,引張鉄筋をSD345から同一径のSD390に変更した
回答:✕
解説:梁の曲げに対する断面算定において,梁の引張鉄筋比がつり合い鉄筋比以下の場合,引張鉄筋が圧縮側コンクリートより先に許容圧縮応力度に達することとなり,この時梁の許容曲げモーメントは,at(引張鉄筋の断面積)×ft(鉄筋の許容引張応力度)×j(曲げ材の応力中心距離)により計算できる.これにおける鉄筋の長期許容引張応力度は,SD345,SD390,SD490ともD25以下の太さであれば215N/mm2,D29以上の太さであれば195N/mm2と同じ値で定められている.よって,引張鉄筋をSD345から同一径のSD390に変更しても,長期許容曲げモーメントは同じ値となる
問題5:鉄筋コンクリート構造の許容応力度計算における片側スラブ付き梁部材の曲げモーメントの算定において,スラブの効果を無視して計算を行った
回答:✕
解説:方形梁が床スラブと一体になって曲げに抵抗するスラブ付き梁部材は,単独の長方形梁よりも,変形が小さい.そのことを考慮して,スラブ付き梁部材の曲げ剛性は,スラブの協力幅baを考慮した有効幅Bを用いた値とする.よって,片側にしかスラブが取り付いていない場合であっても,スラブの効果を無視して計算を行うのは望ましくない
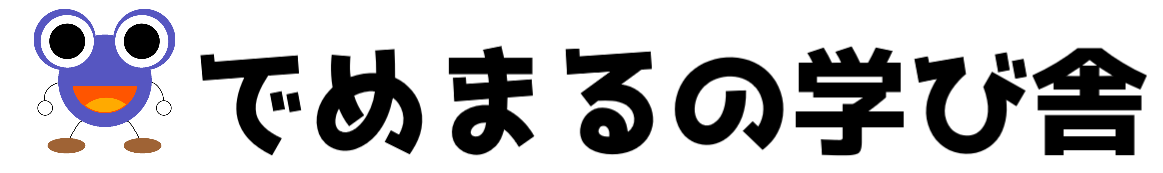

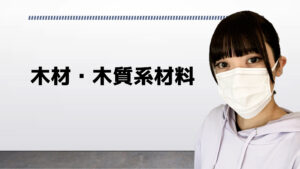
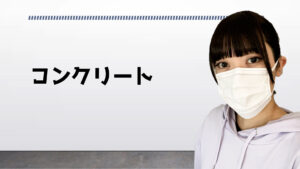
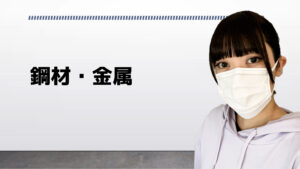
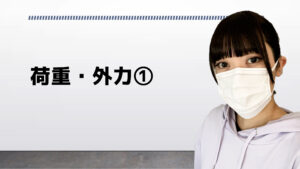
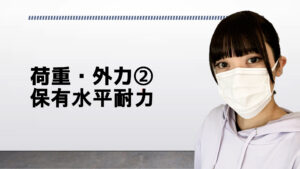
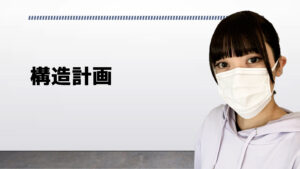
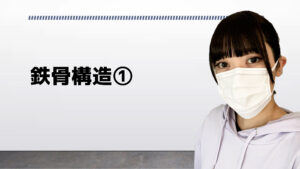
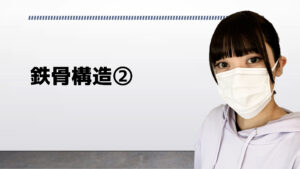
コメント