
一級建築士の構造文章題解説。土質・地盤について解説しています。
※本動画はR7年度改正前に作成した動画です。
動画内で解説した問題
※動画を見るだけではなく、見たら必ず自力で解けるかどうか確認してください。
問題をクリックすると回答が表示されます。
問題1:極限鉛直支持力は,「地盤の粘着力に起因する支持力」,「地盤の自重に起因する支持力」及び「根入れによる押さえ効果に起因する支持力」のうちの最大値とする
回答:✕
解説:第1項は地盤の粘着力に起因する支持力,第2項は地盤の自重に起因する支持力,第3項は根入れによる押さえ効果に起因する支持力を表している.よって,それぞれの支持力の最大値ではなく,それぞれの支持力の和を極限鉛直支持力とする
問題2:支持層が傾斜した地盤の支持杭において,杭の各杭の長さが異なるので,地震時の杭の水平抵抗の検討のために,支持層の近傍で孔内水平載荷試験を行う
回答:✕
解説:孔内水平載荷試験は,水平地盤反力係数を求めるために行う試験である.水平地盤反力係数は,標準貫入試験によって求められたN値からも推定することが可能であるが,モンケン自沈する箇所など非常に柔らかい地層の水平地盤反力係数をN値から推定することは難しい.よって,モンケン自沈する箇所や杭頭から深さ5m程度,または杭径の5倍程度の箇所で孔内水平載荷試験を行うことが多い.つまり,支持層の近傍等のN値の大きな部分では行わない
問題3:地盤のせん断剛性は,PS検層により測定されるS波速度が大きいほど小さくなる
回答:✕
解説:PS検層(弾性波速度検層)は,ボーリング孔を利用して,直接に地盤のP波,S波の速度分布を測定し,その速度値から,地盤の硬軟の判定及びポアソン比,剛性率,ヤング係数等を求めて,構造物の耐震設計資料を得ようとするものである.超高層建築物の設計において,必要とする物理探査の一つである.地盤のせん断剛性は,せん断波速度の2乗に比例して大きくなる
問題4:基礎を支持する砂礫層直下の粘性土層の圧密沈下の特性を把握するために,粘性土の乱さない試料をサンプリングして,一軸圧縮試験を実施した
回答:✕
解説:直接基礎を設計する場合,支持層の下部に粘性土層がある場合,粘性土地盤の沈下特性を検討するには,圧密試験を行う.圧密試験は,側面を拘束した供試体に軸方向に排水を許しながら荷重を加えて圧密状態を測定するもので,圧密降伏応力,圧縮指数,体積圧縮係数,圧密係数,透水係数が求めることができる.圧縮指数・体積圧縮係数は沈下量の計算に,圧密係数は沈下速度の計算に用いられる.一軸試験ではなく圧密試験を行うので誤り
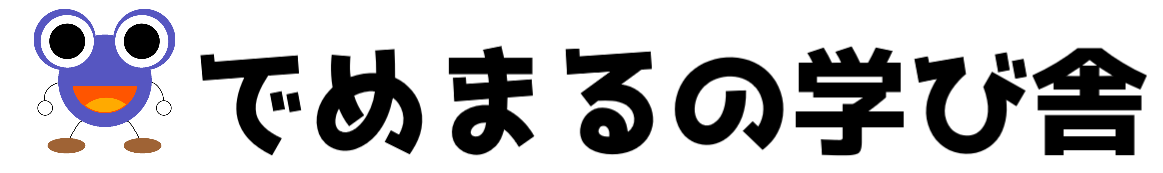

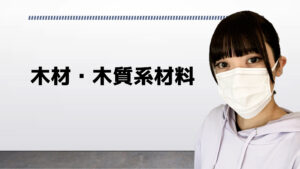
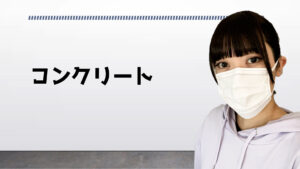
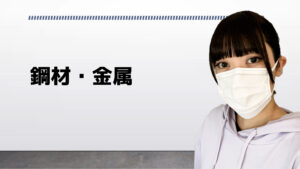
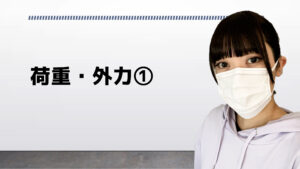
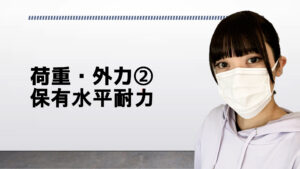
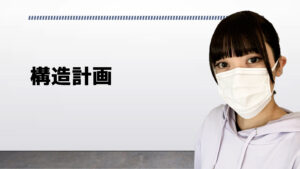
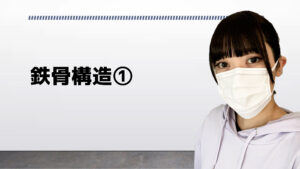
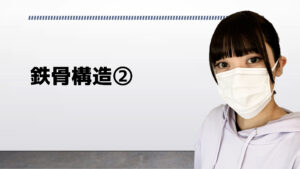
コメント